ハンブルク名物ラプスカウスは船乗りのおかゆ?

ドイツ、北の港町ハンブルクの名物料理として、ハンバーグと並んで真っ先に名前が挙がるのが、「ラプスカウス」。塩漬けの牛肉、ビーツ、じゃがいも、玉ねぎから作られたおじや(またはお粥)と説明されても、そのお味を想像できる人は少ないのではないでしょうか? ラプスカウスの実態に迫ります。
食べるのにちょっと勇気がいる見た目のラプスカウス

©️pixabay_FraukeFeind_labskau
ハンブルクを旅行中、名物料理だというラプスカウス(Labskaus)を食べたくて、波止場のレストランで注文。
そしてテーブルに運ばれてきた一皿。
ぱっと目に入るのは、ピクルスやビーツの薄切りに彩られた目玉焼き。
でも、その下に隠れている生ひき肉のような赤い色をした物体はナニ・・・?
ドイツ人でも、ラプスカウスを一目見て、
「まずそう・・・」
「これ、食べられるの?」
「げげ~っ!」
という人も多いようなのですが、おそるおそるフォークを口に運べば、
「うん、おいしい!」
茹でたジャガイモとコーンビーフを混ぜてマッシュにしたものなので、おいしくないわけがないのです。
が、やはり見た目がちょっぴり「閲覧注意」な感じなのが、マイナスポイントですね。
ラプスカウスはハンブルクのオリジナル料理なの?

©️Schiffergesellschaft zu Lübeck (c) LTM – Ingo Wandmacher
ハンブルクの名物料理ではありますが、実は、ラプスカウスはハンブルクのオリジナルではありません。
ラプスカウスはもともと、ドイツ北部や北欧諸国の船乗りの料理でした。
かつて、帆船で長い航海をしたとき、船上で食べ物を長く新鮮に保つ方法はありませんでした。冷蔵庫などはなかったからです。
そのため、スムチェ(Smutje)と呼ばれる料理人は、船上でも長持ちする食材を使って料理しなければなりませんでした。
船上でも長持ちする食材としては、塩漬け牛肉、ビーツのピクルス、玉ねぎ、じゃがいもなどがあり、これらから作られたお粥状の料理がラプスカウスです。
なぜ、お粥状になっているかというと、当時の船員たちは、長い航海中にビタミンC不足から壊血病にかかることが多く、そのため歯並びが悪くなり、固形物が食べにくかったから、と言われています。
そういう意味でも、ビタミンCを多く含むビーツやキュウリのピクルスをそえるのは、理にかなっているといえるでしょう。
また、ドイツ語でマチェス(Matjes)と呼ばれるニシンの塩漬けを添えるかどうかも、地方によって異なるようです。
ハンブルクと同じハンザ都市のひとつのリューベックでは、マチェスを添えますが、少し北にのぼったフレンスブルクなどではそうではないようです。
ラプスカウスの言葉の由来は?

「ラプスカウス(Labskaus)」という言葉の由来は不明です。いくつかの解釈がありますが、それらはすべて19世紀に入ってから言及されているものです。
一つには、英語を起源とするロブスコウス(lobscouse)から来たものだとする説があります。これは、「ぶこつ者、いなか者」を意味する英語loutから来た「lout’s course ロウズコース(いなか者の食事)」がなまって「lob’s courseロブズコース」になったということです。
また別の説には、牛肉の一部位であるラッペン(独語: Lappen、英語: flank)に、低地ドイツ語でボウルを意味するカウス(Kaus)がくっついたもの、という説もあります。
さらに、ノルウェー語で「噛みやすい」という言葉が語源だという説もあります。
さらに、さらに、バルト諸国のラトビア語、リトアニア語でそれぞれ「良いボウル」という意味の言葉が語源だとする説もあり、真相は闇の中です。
ラプスカウスの作り方

お店によって少しずつ違うラプスカウス©️Chiyo Kamiya
それでは最後に、ラプスカウスの作り方をご紹介しましょう。
ラプスカウスの材料
- コーンビーフ1缶(約340g)
- 玉ねぎ2個
- じゃがいも500g(男爵系)
- ビン詰めのビーツ
- キュウリのピクルス
- 月桂樹の葉、クローブ、塩、コショウ
- 油またはバター
- 卵
- ニシンの塩漬け
ラプスカウスの調理法
- 玉ねぎ一個は皮をむき、月桂樹の葉とクローブを突き刺して、塩水で約40分間茹でる。
- 約20分後、玉ねぎを茹でている鍋に皮をむいたジャガイモを加える。
- もう一つの玉ねぎをさいの目に切って、コーンビーフと一緒に少量の油を入れたフライパンで炒める。
- フライパンに玉ねぎを茹でたゆで汁を少量加えて火を通す。
- 40分後、鍋から玉ねぎを取り出し、ジャガイモの水を切る。*この時、ゆで汁を少し取っておく。
- じゃがいも、炒めたコーンビーフと玉ねぎを混ぜる。取っておいたゆで汁を加えて、好みの硬さにする。
- コショウと塩で味を調える。
- 目玉焼き、ピクルス、ビーツ、ニシンの塩漬けを添えてサーブする。
レシピは、ハンブルク市公式サイト www.hamburg.de/ に掲載されていた公式レシピです。 ラプスカウスで、ハンブルクの港を感じてくださいね。

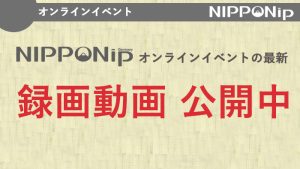
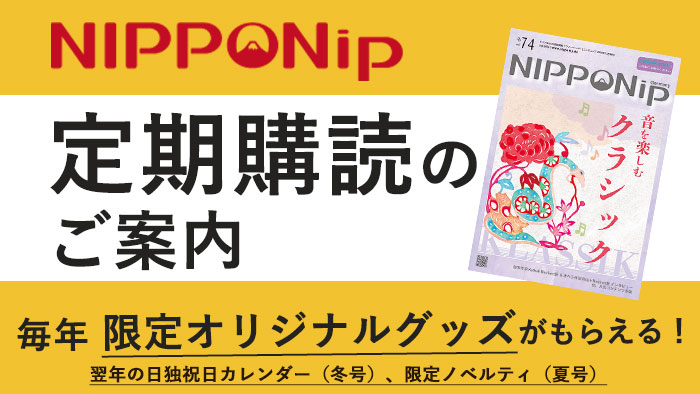

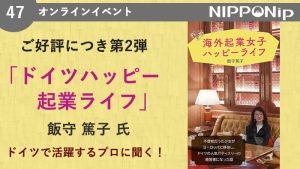

 世界中どこでも使えるe-SIM 【PR:Affiliate: UBIGI
世界中どこでも使えるe-SIM 【PR:Affiliate: UBIGI 