季節のめぐみをいただこう! ドイツ11月の野菜と果物

11月になりました。どんよりと曇ったお天気の日が多くなり、冬の訪れを体感する直です。季節の野菜も、夏は葉物野菜や実もの野菜が豊富でしたが、冬季は根菜がおいしくなる季節ですね。11月が旬の野菜と果物をご紹介します。
Obst :11月が旬の果物
梨(Birnen ビルネン)

©️pixabay_PIRO4D
梨はリンゴと並んで、最も人気のある種類の果物の1つです。 ドイツでは、小腹がすいたときなどにもよく食べられます。
梨は酸味が少ないため、生食のほか、コンポートやケーキ、タルトなどお菓子の材料にも使われるほか、サラダとして、チーズと合わせて、またはジビエや家禽などの肉料理のサイドディッシュにしたりなど、様々な用途に使われます。
その際のスパイスには、クローブやシナモン、ジンジャーなどがよく合うと言われています。
Gemüse : 11月が旬の野菜
セロリアック(根セロリ)(Knollensellerie クノーレンセレリー)

©️pixabay_pixel2013
強い香りを持つ根菜のひとつセロリアックは、スープやソース料理などに使うと、食欲をそそる味わいを加えることができます。
通常、塊茎の直径は20センチほどのものが出回っており、重さは1キロ近くなるものもあります。小ぶりなもののほうが繊維が少ないので、味はよくなるようです。
よく洗い、厚めに皮をむいてから薄切り、またはサイコロに切ったセロリアックに、火を通してスープやピューレ、セロリシュニッツェル(後述)として楽しめるほか、生のままウォルドルフサラダ(後述)にするなど、広範囲に使える野菜です。
セロリシュニッツェル Sellerieschnitzel のレシピ
- セロリアックの皮をむき、厚さ約1.5cmにスライスします。
- 沸騰した塩水で約10分間調理してから、冷まします。
- セロリアックのスライスを小麦粉、溶かした卵、パン粉の順でまぶします。
- 鍋にバターとオイルを少し熱し、衣をつけたセロリアックのスライスを両面で約5分間、黄金色になるまで炒めます。
- サーブする前に塩とコショウで味付けしてください。付け合わせには、フライドポテトやマッシュポテトがよく合います。
ウォルドルフサラダは、19世紀の終わりにニューヨーク市のウォルドルフアストリア(Waldorf-Astoria)ホテルの前身であるウォルドルフホテルで作成されました。
このホテルは、バーデン=ヴュルッテンベルク州にあるウォルドルフ(Walldorf)からのドイツ人移民の子孫であるウィリアムおよびジョン・ジェイコブ・ウォルドルフアスター(William & John Jacob Astor)によって設立されました。
1896年にこのホテルのキッチンで生まれたセロリを使ったサラダが、ウォルドルフサラダとして世に出たのです。
ウォルドルフサラダのレシピ
- リンゴとセロリまたはセロりアックを細切り(ジュリエンヌ)にする。
- 1.を少量のレモンジュースであえ、刻んだクルミ(適量)を混ぜてからマヨネーズと生クリームを入れます。
レシピによっては、パイナップルやデーツ(西洋棗)などが入ることもあるようです。
パースニップ(Pastinaken パスティナ―ケン)

©️pixabay_Ulrike Leone
一見、白いニンジンのような趣のパースニップは、ドイツでは一時、忘れられた野菜となっていましたが、ここ数年またキッチンにカムバックしました。
ニンジンよりミネラル含有量が多く、また多く含まれたでんぷんが過熱すると糖分に変わるので、じっくりと低めの音頭で加熱するオーブン料理などにすると、その滋養あふれるナッツを思わせるおいしさが味わえます。
切って蒸したパースニップは、すっきりとした後味があるので、ラム料理やジビエ、牛肉料理の付け合わせとして好まれています。じゃがいもといっしょにピューレにするのもおいしいものです。
パースニップは生でも食べることができ、粗くすりおろしたものをサラダに加えるのもいいアイディアです。
加熱したものは消化がよいので、ベビーフードなどに利用されることもあります。
Salat 11月が旬のサラダ
ノヂシャ(Feldsalat フェルドザラート)

©️pixabay_ejaugsburg
ドイツ語で「平原のサラダ」という意味になるノヂシャは、野生種が小道や野原の端で育っていたという事実に由来するそうです。つまりこのサラダ菜は長い間ドイツでは雑草とされていました。やがて、そのナッツのような風味が注目され、サラダ菜として栽培されるようになったのです。
日本語でもノヂシャと呼ぶのは、野にはえるチシャという意味なので、通じるものがありますね。
もと雑草だったというだけあり、他にもいろいろな呼び名のあるサラダ菜で、アッカ―(農地)ザラート(Ackersalat)、マウスオア(ネズミの耳)ザラート(Mausohrsalat)、フォーゲル(鳥)ザラート(Vogelsalat)、ラプンツェル(Rapunzel)など、各地で異なります。
| ノヂシャの別名 | |
|---|---|
| Feldsalat | フェルド(平原)ザラート |
| Ackersalat | アッカ―(農地)ザラート |
| Mausohrsalat | マウスオア(ネズミの耳)ザラート |
| Vogelsalat | フォーゲル(鳥)ザラート |
| Rapunzel | ラプンツェル |
ビタミンと鉄分を含み、冬の寒さに強く、マイナス15度までは耐えられるそうなので、緑の少ない冬の季節には重宝する野菜です。
生でサラダにしてたべるのが主流ですが、特にベーコンやカッテージチーズとの相性がいいようです。また、温かいポテトサラダに混ぜて食されることもドイツでは多いようです。
根の部分に土や砂が残っていることもあるので、食べる前によく水洗いをしましょう。また、足がはやく腐りやすいので、できるだけ早く食べるようにした方が良いでしょう。
梨とノヂシャのサラダのレシピ
- ノヂシャを洗い、よく水気を切ったら、お皿の上に並べます。
- ベーコンを油をひかないフライパンで炒め、カリッと茶色に仕上げます。
- 梨を洗い、芯を取り除き、8つ切りにします。
- マッシュルームの汚れを取り除き、スライスまたはウェッジにカットします。
- 梨とキノコをノヂシャの上に均等に並べします。
- 炒めあがったベーコンを鍋から取り出し、ペーパータオルで余分な脂肪を取り除き、少し冷ましてから細かく砕いて、サラダの上にかけます。
- 細かく切ったゴルゴンツォーラチーズ Gorgonzolaをかけて、ヴィネグレットドレッシング(フレンチドレッシング Vinaigrette)をかけてお召し上がりください。
*チーズはお好みでロックフォールを使ったり、全く使わなくてもOKです


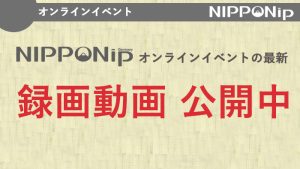
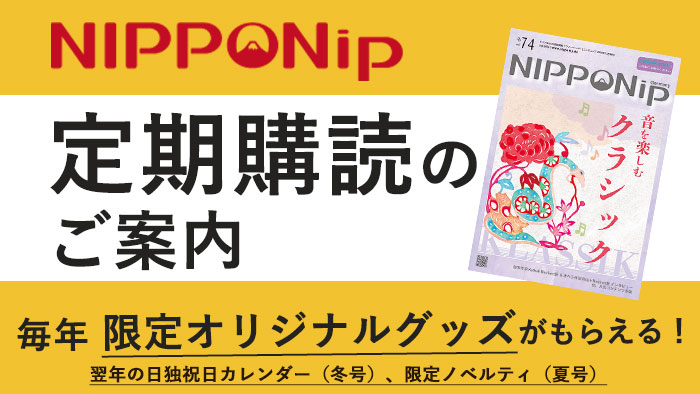


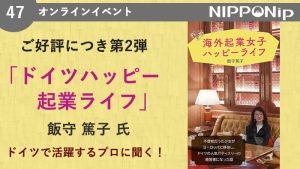
 世界中どこでも使えるe-SIM 【PR:Affiliate: UBIGI
世界中どこでも使えるe-SIM 【PR:Affiliate: UBIGI 